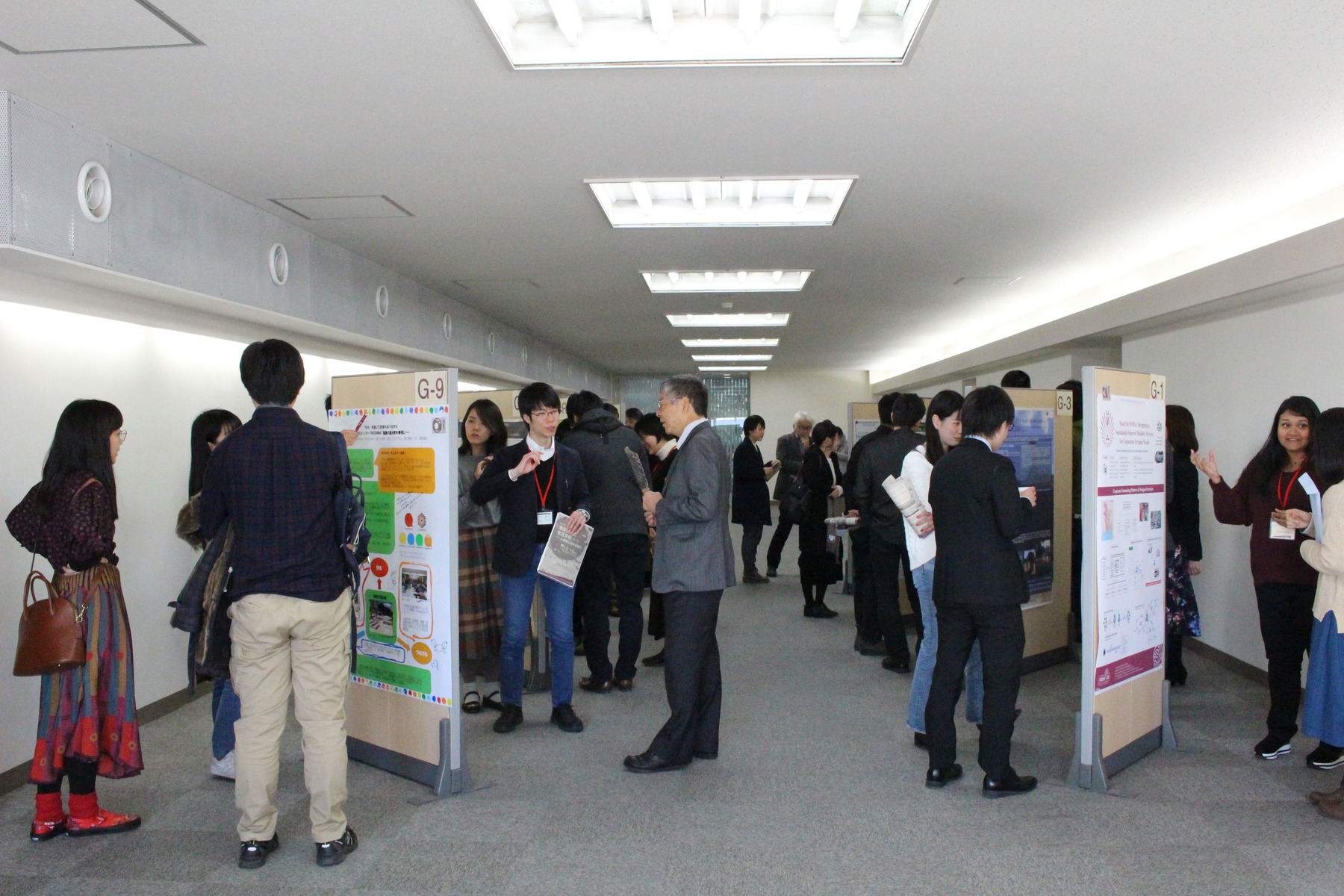総合地球環境学研究所との合同カンファレンス「地球環境と生活文化」 報告 宮田 晃碩
- 日時
- 2018年12月15日(土)〜16日(日)
- 場所
- 東京大学駒場キャンパス(15日)、本郷キャンパス(16日)
- 主催
- 東京大学大学院博士課程教育リーディングプログラム「多文化共生・統合人間学プログラム(IHS)」教育プロジェクトH「生命のポイエーシスと多文化共生のプラクシス」
総合地球環境学研究所(地球研)との合同カンファレンスに参加するのは、今回が三度目である。昨年、一昨年のカンファレンスを通じて地球研のことを知った私はその活動に大変興味を抱き、じつは今年度九月末から三ヶ月間、京都盆地の北の縁に位置する地球研に滞在させていただいたのだった。これはIHSで学外インターンシップが課せられているので、その行き先にと思い地球研とIHSの先生方に相談し実現していただいたものである。地球研では「オープンチームサイエンスプロジェクト」にプロジェクトメンバーとして参加させていただき、プロジェクト内外で豊かな経験を積むことができた。今回の合同カンファレンスは私にとって、地球研で学び考えたことを多くの人と共有する機会でもあった。そこで私は、上記プロジェクトリーダーの近藤康久先生と共著で「生活文化が「知」となるために――オープンチームサイエンスという方法論」という題でポスターセッションに出展したのである。主旨は「オープンチームサイエンス」の方法論を紹介するということであったが、これに関連して私自身が地球研で考えたのは根本的には「知とは何か」ということであったから、この観点から「地球環境と生活文化」という今回の全体テーマに関して寄与したいと考えたのである。

1. オープンチームサイエンスという方法論
報告書としては遠回りになるが、初めに私自身の発表について振り返り、どういう関心から参加したかを確認したい。
地球研には様々な実践プロジェクトがあり、それぞれが各現場で学際的研究を行っているが、私がメンバーとして参加した「オープンチームサイエンスプロジェクト」はいわばそれらのハブとなって、多分野の協働、地域社会との連携に関する包括的な方法論を構築することを目指している。そこでの大きな問題意識は、「現実の問題に対する多様な主体の間の認識のずれをどう乗り越えるか」というものである。特に環境問題に取り組む場合、様々な学問分野の協働が必要とされるばかりでなく、市民、行政、さらにその中でも様々な関心や理解をもった主体と協働する必要があるため、そこでの問題理解の隔たりをどう乗り越えるかということが根本的な課題となる。この課題に関して、超学際研究(transdisciplinary research)の理論的研究を参照しながら様々な実践を反省的に捉え、方法論の仮説を提示し、実践に活かしつつ検証していく、というのがこのプロジェクトの目的である。
プロジェクトでは既に具体的なアプローチをまとめ、効果測定の方法を開発中である。これに対し私自身は、そこで提示される「オープンチームサイエンス」という方法論の究極的な目標が「知と未知についての観方を変える」という点にあるだろうと思っている。図式的に言えば、乗り越えられるべき古典的な観方は次のようなものである。即ち、知識とはそれぞれのディシプリンの内で生産されるものであり――というのも問題設定は各ディシプリンのうちで為されるのであるから――そこで生産・蓄積された知識が環境問題に適用される、そしてその際他のディシプリンとの協力および社会との交渉が要求される、といった観方である。これに対してオープンチームサイエンスの理念は次のような変更を迫る。即ち、第一に諸科学のディシプリンを社会の多様な主体と対等の位置に置き、それぞれ固有の関心を持つものとして扱うこと、そして第二に環境問題を、それら多様な主体の〈あいだ〉に生ずるものとして捉えること、その帰結として第三に、環境問題に対する知識を多様な主体の〈あいだ〉で生成するものとして捉えることである。各主体は、他の主体について必ずしもよく知っているわけではないし、他の主体が有する知識についても十分知らないことが多い。これは当然のことである。だが環境問題に取り組む際、この当然のことをいかに受け止めるかが重要になる。環境問題は住民にとっても科学のディシプリンにとっても、まず未知の異変として現われてくるだろう。その未知にいかに向き合い対処するかということがそれぞれにとっての課題となるのだが、そこでは同時に、いかにして他の馴染みのない主体と関わるかということも課題とならざるをえない。その意味で「未知」は多数の主体の「あいだ」に存するのであり、まさにその「あいだ」で共に未知に直面し、共同的な知を作り上げる方法がオープンチームサイエンスなのだと言うことができる1。

2. 民具・民藝をめぐる基調講演
さてこうした理解・関心から、今回の合同カンファレンス全体を振り返ってみたい。というのもこの企画自体が、超学際研究の性格を有すると考えられるからである。まずポスターセッションには、文化人類学、工学、言語学、生態学など多様なディシプリンからの出展があった。そしてその参加者の間で問題理解を共に掘り下げるための対話のセッションが二度設定され、「地球環境と生活文化」を共通のテーマとして対話が行われた。さらにこのテーマに具体的にアプローチするため、明治大学の鞍田崇先生、良品計画の矢野直子さんの基調講演と対談があった。これらを通じて参加者たちのあいだに何が生じたのか、何が変容したのかということがここでの関心となる。

第一に、矢野さんと鞍田先生のお話を振り返りながら「地球環境と生活文化」というテーマについて考えてみたい。矢野さんからは、良品計画のフィンランドにおける最近の展開を導入として、「無印良品」の理念が語られた。いまや「無印」はブランド的な価値を持っているが、その出発点は80年代当時の消費社会へのアンチテーゼにあった。つまり素材の選択、工程の点検、包装の簡略化を通じて「感じ良いくらし、感じ良い社会」のあり方を模索しようということである。その表現としてのシンプルなデザインは、当初人々の眼にアバンギャルドなものと映り、関心を集めたのである。そしてこの理念は衣食住の全範囲にわたる。実際フィンランドでは現在自動運転車両のデザインに携わっており、最近では “MUJI HOTEL” として深圳・北京でホテルも展開している。これらは決してブランド価値に乗っかった拡大戦略というわけではなく、むしろ当初からの「くらしをデザインする」という理念の実現であるという。手のひらサイズの道具から社会全体に至る生活の有機的な連関に対して、「デザイン」という観点からアプローチを試みているのだ。これは「地球環境と生活文化」という二項を繋ぎうる観点かもしれない。また一方で鞍田先生からは、柳宗悦の「民藝」をめぐる思想・活動の紹介があり、その観点から生活文化を捉え直す可能性が示唆された。より自然に馴染んだ生活を見いだすための通路として「民具」があり、そこに審美的価値を見いだしたものとして「民藝」がある。いわば暮らしの切片に美的規範を持ち込むのが「民藝」の考え方であり、この点良品計画における「デザイン」と通ずるものがあると言えよう。百年の時を隔てて、共通点は他にも見出される。民藝は決して守旧的な動きとしてではなく、むしろ時流に抗うアバンギャルドとして打ち出されたということである。こうした態度に共鳴してオフ・グリッドな生活を模索する現在の若い世代の活動も紹介された。民藝のこの「反動的」な性格を考えるとき、鞍田先生が「インティマシー」即ち「親しみ」という概念を以てその運動を語ることは興味深く思われる。我々はおそらく、絶えず親しみを失った暮らし方へと疎外される傾向があり、その傾向への反動として「親しみ」を求める運動がアバンギャルドな動きとして現われるのだろう。そうだとすると、我々は何故「インティマシー」から離れていってしまうのか、その傾向に抗して民藝的な「インティマシー」はどのように(反動的でありながら)社会全体にとって馴染みよいものとなり得るのか、ということが問われねばなるまい。そうでなければ形だけのアバンギャルドということになる。「インティマシー」という概念が、自然と人との関係のみならず、多様な人間のあいだでどのように働きうるかということも問われねばならない。実のところ、民藝という〈道具〉に着目することは明らかに、人間関係についての考察の端緒となりうるだろう。道具はそれ自体で規範性・社会性を備えるからである。それは市場経済を前提としてもなお有効な観点であるに違いない。加えて対談で示唆されたのは、道具との付き合いが生み出す独特の時間性であった。道具は単に即席の便利さを提供するのでもなければ、一時的な美意識を満足させるのでもない。むしろ経年変化や手入れなどによって、生活そのものに厚みや愛着を持たせうる結節点となるのである。時間に対するこのような感受性は地球環境への関わり方を考え直す上でも重要な契機となろう。

地球環境と我々の関係は端的に言えば、我々がそこに「住んでいる」ということである。「地球環境と生活文化」というテーマは、「我々はどのように住んでいるのか、どのように住むことができるのか、どのように住むべきなのか」という問いを扱うものに他ならない。お二人の基調講演はこの問いに対する具体的なアプローチを提示するものであった。そこで語られた事柄は、様々な関心や方法を有する参加者のあいだの “boundary object” として働いたと言えるのではないか。 “Boundary object” とは超学際研究において、多様な主体の隔たりを媒介する対象を指す語である。実際我々は皆何らかの生活を営んでいるのであり、どのような考えを持っていようとこれについて語ることができるだろう。従ってカンファレンスのテーマおよび基調講演は、今回の超学際的な取り組みにおいて、一つの boundary object を提供したと思うのである。ただしこれが十全に働きうるか否かは、どのように対話をデザインするかに依存する。そこで次に、この「対話」について振り返りたい。
3. 地球環境と生活文化をめぐる哲学対話
全体のプログラムをあらためて振り返ると、まずポスター出展者同士のポスター発表、一回目の対話、昼休みを挟んで一般参加者も含めてのポスターフラッシュ発表とポスター展示、続いて基調講演と対談があって、一日目は閉会となる。二日目の午前には全体を踏まえてポスター出展者同士の第二回の対話が設定された。この二回の対話は「哲学対話」の形式で、つまり一定の結論を目指した議論ではなく、自由な対話を通じて問いを深めるという仕方で行われた。対話の内容を細かに振り返ることはしないが、一回目の対話で私が参加したグループでは「地球環境と生活文化はどのように関係しているのか/そもそも分けることができるのか」という問いを、二回目の対話では「どうすれば “スローな生活” が可能なのか」加えて「お金がなければ文化的生活はできないのではないか」という問いを扱った(人数の関係で、それぞれ二つのグループに分かれて行った)。いずれも漠然とした、どうすれば「答え」が示されたことになるのかはっきりしない問いである。だが「地球環境と生活文化」というテーマに関して、この形式は非常に良かったと思う。
そもそも生活文化という、当事者にとって「当たり前」になっていることをあらためて考察の俎上に載せるためには、形式的な問題を矢庭に立てるのではなく、まず日常的に抱いている素朴な考えを析出しつつ、同時にそれを問いのもとに置く必要がある。なぜなら何を問題にすべきかということが、そもそも問われねばならないからである。例えば一回目の対話では、「環境」や「自然」といった語を用いるとき我々はその語が指示するものとの関係をどのように捉えているのかといった問いから、そうしたものを「他者」と捉えるならば「文化」はそれら「他者」との付き合い方を含んでいるのではないか、然りとすれば自然や環境の「他者性」は人間のそれとどう異なるのか、といった問いへと話が展開していった。また二回目の対話では、「そもそもスローとは何か、我々はスローな生活をしていないのか」といった問いから、人間関係における時間の経験と自然との付き合いにおける時間の経験との連関、また複数の時間の間を移行する時間、といった事柄へと話が展開した。ここには明らかに、日常生活への問いの深化が見られる。それは決して抽象的な語句の戯れに話題が遊離していったということではなく、むしろ話題の展開のなかではそのつど、各々の具体的な経験が語られ共有されているのである。

対話のセッションのなかで話し合われたことは、ほとんどがオープンな問いの形で残されている。私はこのことが重要であると思う。なぜならこのことは、参加者各人が自分自身の関心や方法を保ち、各自の活動に従事しつづけることを妨げないが、それにも拘らずこれらの問いに触発されることを可能にするからである。たとえ意見や信条が共有されなかったとしても、このように問いを共有し、問いのもとに連帯するということは可能であろう。この問いを通じて、他のディシプリンに接近するということも可能である。その場で答えを目指さないこの対話の方法が結局のところいかなる「成果」を生み出すかは、もちろん長期的に捉えられねばならず、共有された問いがいかに繰り返し呼び起こされるかにかかっているだろう。
4. まとめと展望
ここまで、「地球環境と生活文化」というテーマのもと基調講演で提示された事柄を boundary object として、また二回の対話セッションを参加者の協働を促す契機として振り返ってきた。今回の企画を「超学際研究」の一例として見るならば、課題はおそらく、取り組みの継続性に求められるだろう。なぜならここで生じた知ないし何らかの変容は関与者の〈あいだ〉に存するものであり、この〈あいだ〉をいかに耕してゆけるかという点にその意義が懸かっている、と言えるからである。具体的な地域での超学際研究ならば、その〈あいだ〉はまさに問題の起こっている地域、関与者の住んでいる地域に定位される。今回のような、個別的地域における繋がりを持たない研究者同士の場合には、いったいいかなる〈あいだ〉の持続性を構想することができるだろうか。研究の「場所」をどのように作ることができるだろうか。地球研とIHSの合同カンファレンスは、このような問いに直面し、その可能性を模索しつつあると言えるだろう。継続性のみならず、その〈あいだ〉をいかに拡大してゆけるかということも課題となる。この企画を一つの里程標として、さらに地球研とIHSないし他の大学との関わりが豊かになればと願っている。私自身、そこに貢献できれば幸いである。
最後に、今回の企画に関わられたすべての方、また地球研でのインターンシップを支えてくださったすべての方に心から感謝を申し上げたい。