
IHS学生シンポジウム「知の協働はいかにして可能か」 報告 宮田 晃碩
- 日時
- 2017年9月12日(火)
- 場所
- 東京大学駒場キャンパス18号館4階コラボレーションルーム1
- 主催
- 東京大学大学院博士課程教育リーディングプログラム「多文化共生・統合人間学プログラム(IHS)」教育プロジェクト2「共生のプラクシス──市民社会と地域という思想」
- 発表
-
田中瑛「生きづらさの結節点としての福祉番組──公共放送とラディカル民主主義の接合に向けて」
宮田晃碩「ケアの現象学から『間柄』の倫理へ──哲学と医療社会学」
Hiroko Tanabe ‘Reconsideration on the Sense of “Our Places” through Reading Theatrical Texts and Maps’
Marcin Wróbel ‘History Textbooks: Cooperation between Germany and Poland - Implication for East Asia?’
三田寛真「大学を飛び出す言葉の科学~人工知能時代における認知言語学~」
以下では「第1回統合人間学シンポジウム」と題して行われた学生シンポジウムに関して、(1)その開催の経緯と概要、(2)自分自身の反省、(3)全体を振り返っての気付きと反省、という形で報告する。
1. 開催の経緯と概要
今回の学生シンポジウムはもともと、参加者がそれぞれの研究を専門外の人たちにも伝わるよう発表する、という機会として設けていただいた企画である。それを、準備の段階で「ただ研究内容を伝えるだけでなく、それぞれの研究がどのように互いに関わり得るか、という問題意識を共有して会全体をデザインしたい」という学生側の意見を汲んでいただき、「知の協働はいかにして可能か」という副題を冠する会が催されることとなった。まずこうした柔軟なイベントの機会を用意してくださったスタッフの皆さまと、協力して準備に取り組んでくれた参加者の皆さんに感謝申し上げたい。
今回のシンポジウムの形式面での特徴は、それぞれの発表においてディスカッサントを一名ずつ依頼し、発表に対するコメントないし議論の提起をいただいた、ということである(ディスカッサントとしてご参加くださった皆さまにも深く感謝申し上げたい)。ディスカッションがどのように行なわれるかについては、各ディスカッサントの裁量に委ねられた。これはそれぞれ興味深い仕方で活かされたと思う。例えば具体的な分析に対してそれを整理する理論的な枠組みを提示しフロアと共有する、という仕方でなされたり、あるいは大学の外で活動している観点から、実際に可能な応用を示すという仕方でなされたりした。今回参加した5人の発表者は専門を異にしているが、「他領域との協働」という問題意識を共有して発表を工夫する、という点で一つの課題を共有できていたものと思う。
2. 自分自身の反省
自分の発表を振り返ると、「他領域との協働」を強く意識したことは良い方向に働きながらも、大きな課題も明らかになったと感じる。私自身の専門は現象学で、特にマルティン・ハイデガーや和辻哲郎のテクストを読解しながら自己と他者の関わりを考察する、ということに取り組んできた。これは基本的に、理論的な研究ということになる。だが今回は、理論的なレベルでの考察がどう実践的な問題と結びつくかということを考えるため、あえて(ちょうど関心を抱きつつあった)「看護ケアの現象学」に手を伸ばし、その実践について和辻の『倫理学』の視座から何が言えるか、ということを論じた。
これが特に実りあるものとなったのは、IHS修了生の山田理絵さんにディスカッサントとしてご参加いただいたおかげである。山田さんは精神医療の社会学を専門とされており、歴史資料の調査とフィールドワーク調査を重ねながら研究されている。その視点から、私の発表に対し批判的かつ生産的な問題提起をいただいた。また当日ご臨席くださったフロアの方々からも質問やコメントをいただき、大変実りある機会となった。特に実際に看護師として働いていた方からもコメントをいただいたことは望外の喜びであった。こうして様々な方向へ議論が開けたことは、あえて実践的な領域を取り上げたことの成果だったと思う。惜しまれるのは、私自身がその実践について論じるための理論的な背景を十分学びきれていなかったということである。ある実践領域について論じ得る文脈はかなり入り組んでおり、それについて熟知するには腰を入れ時間をかけて研究する必要がある。それほどの準備ができていなかったため、寄せていただいた質問に十分答えることはできなかったように思われる。ただ、これも収穫とは言えるだろう。実践について論じることの困難を知った、ということが一つ。もう一つは、少なくとも議論の端緒をこれによって掴んだはずであり、私自身がこの領域を学んで議論を継続することが可能だ、という感触を得たことである。
3. 全体を振り返っての気付きと反省
全体を振り返って特に良かったと思うのは、IHSの外部からもディスカッサントや聴講者として、多くの方がご参加くださったことである(当日参加してくださった皆様に感謝申し上げたい)。
しかし同時に、会場の全体で問題意識を共有して議論する、ということの難しさにも直面させられた。「知の協働はいかにして可能か」というテーマが共通の関心となることは間違いないのだが、各々が「協働」といって思い描くものや直面している課題は、それぞれに異なっているだろう。それを前もって統一することはできないし、そもそも各人において明らかになっているとも限らない。だからこそ、この学生シンポジウムは、それ自体が「知の協働」を実践する、すくなくともその端緒を見出すものでなければならないのである。その難しさは具体的には、次の三点に見出された。即ち、発表者とディスカッサントとの応答をどのようにフロアに開いていくか、個々の発表の繋がりをどのように確保するか、またどのような全体ディスカッションをデザインするか、ということである。
実のところ「個々の発表の繋がり」に関しては、今回部分的に実現されていたことがある。偶然のようにも見えるのだが、おそらく必然的なことだった。それは、どの発表も何らかの意味で「公共性」を問題にしていたということである(紙幅の都合により詳細を紹介することはできないが)。こうした「公共性を問い直す」という問題関心が今回の発表に通底していたのは、おそらく、準備の段階から共有されていた問題意識によるものだろう。それぞれの発表者が、自分自身の研究はどのように公共的に位置づけられ、あるいはどのように公共性を創出し得るか、ということを志向していたのだと思われる。
このような問題意識の共有が実現されていたことは、今回の成果の一つだと言える。だがこれは未だ曖昧なものであって、明示的な議論に発展させることは今後の課題になる。
そのためには、議論の場をどのようにデザインするか、ということがさらに模索されねばならない。今回のような会において私が重要だと思うのは、その会の後にまで議論が続いていくということである。成功した議論というものがあるとすれば、それは何か一つの結論を提示し得たものというより、むしろその議論がはじめてある問題の地平を切り開いた、といったものだろう。それさえできれば、議論の場はその会に留まらず、別の場所でも展開されたり、個別的な研究の方向性を問い直したりし得る。
「知の協働はいかにして可能か」という今回のテーマは、それぞれの発表において様々な形で吟味され、意義ある結果を示したように思う。ただしこれが一つの議論のレベルを提示し得たかというと、そのためにはさらに対話が必要であるように感じる。発表のテーマが直接関連している必要はないのかもしれない。それぞれの視角や取り組みが問い直されるような共通した議論のレベルを発見することができれば、おそらくすべての人にとって意義ある会となるだろう。その議論のレベルとは例えば「研究はどのように将来の世代を顧慮すべきか」というものであったりするかもしれない。
あるいはもちろん、共通した具体的なテーマや問題事象を設定することもできる。いずれにせよ、どのように会をデザインするかという点を含めて、今後の「第2回統合人間学シンポジウム」以降へと活かしていければと思う。あらためてこうした機会を下さり、また関わってくださったすべての方々に感謝申し上げたい。






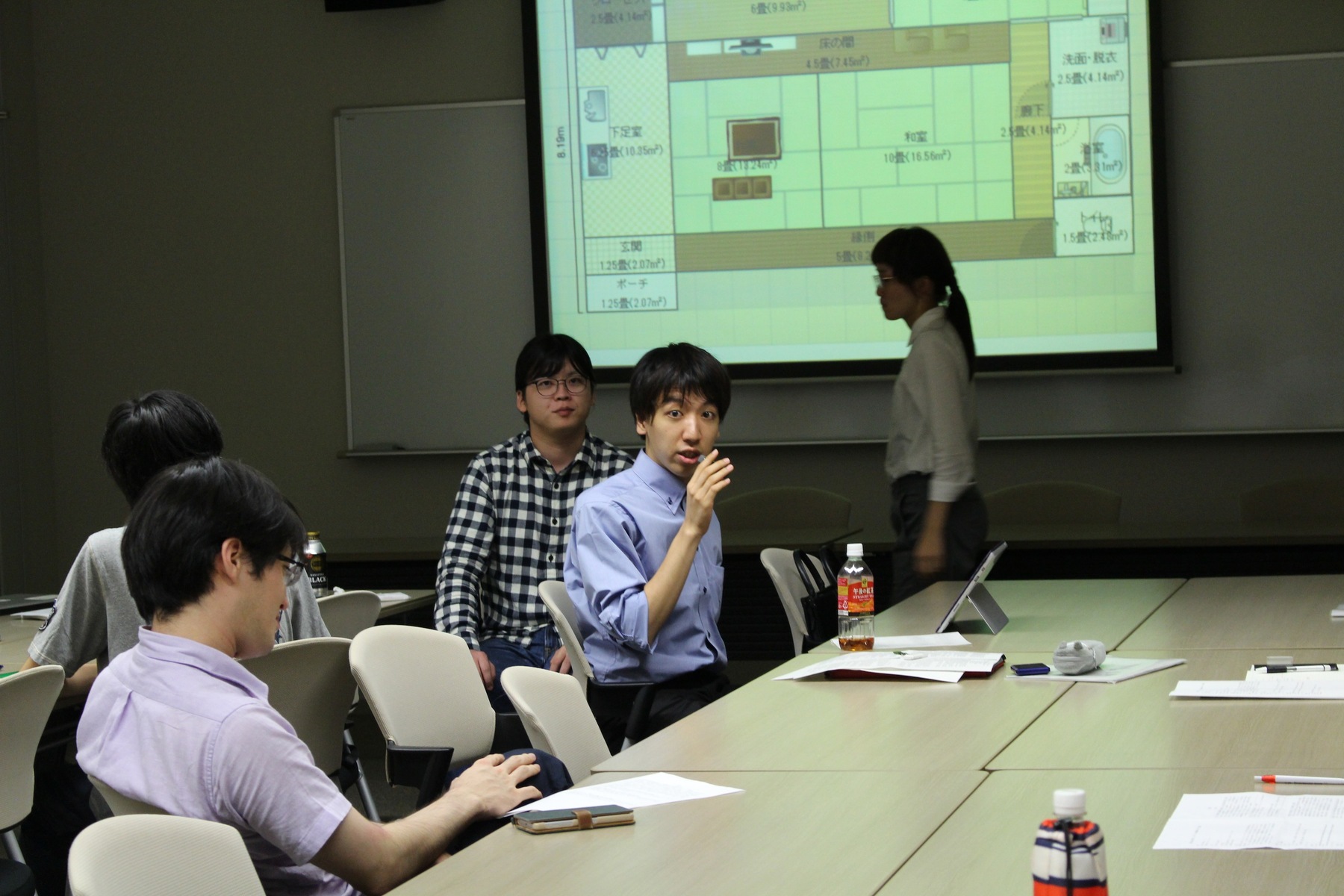
報告日:2017年10月18日


