
徳島県神山町研修報告 吉田 直子
- 日時
- 2017年3月10〜13日
- 場所
- 徳島県名西郡神山町
- 主催
- 東京大学大学院博士課程教育リーディングプログラム「多文化共生・統合人間学プログラム(IHS)」教育プロジェクト5「多文化共生と想像力」
報告者は3月10日から3泊4日で徳島県名西郡神山町を訪れた。神山町は、1955年には人口が2万人を超えていたが、現在では6000人を切っている典型的な過疎の村である。しかしNPO法人グリーンバレーの大南信也氏は、過疎化の流れを受け入れながらも、その「質」を変えようとする「創造的過疎」を提唱し、地域の人々や行政をもまきこむユニークな実践を町づくりに取り入れてきた。象徴的なのは、神山町に国内外のアーティストを招聘し、町内で地域の人々とともに作品づくりにとりくんでもらう「神山アーティスト・イン・レジデンス」や、手に職を持った人々の移住を推進する取り組みであろう。単に住民の数を増やすことを目指すのではなく、多様な人々を呼び込むことによって町の活性化を図ろうとするものである。過疎に悩む農村への移住というと、通常は農業従事者の移住を意味することが多いが、神山町の場合は「これからまちに必要な人材や商い」に貢献する移住者を募るのであって、移住者=農業従事者を求めるわけでは必ずしもない。山村でありながら高速ブロードバンド網が張り巡らされていることもあり、町のはたらきかけによりIT関連企業や徳島県庁などがサテライトオフィスを構えていることでも知られる町である。
その神山町での4日間の研修を振り返る。まず初日は移住者が経営する古民家を改築したピザ屋で昼食をとったあと、今回共に研修を行った同志社大学のメンバーと合流、神山町の地域創生事業を牽引してきた大南氏から、NPO法人グリーンバレーの活動のはじまりとこれまでの経緯を伺った。その後、町内にある複数のサテライトオフィスを訪問した。2日目は、神山町役場と民間との協働により設立された一般社団法人神山つなぐ公社の杼谷氏から、神山町地方創生戦略についてのレクチャーを受けたのち、特に神山町の「食」に焦点を当て、再び町内を回った。まず地域の食材を使った食事を提供する食堂「かま屋」を訪れ、その運営を行っている「フードハブ・プロジェクト」の概要について説明を受けた。午後からは、無農薬栽培や有機栽培を手掛ける農家さんの畑や棚田、また神山町が日本一の生産量を誇るすだちを栽培する農園を見学し、農家の方々(地域の出身者から移住者まで)から現状を伺った。また里山の価値を見出し、つなぐことを目指すNPO法人里山みらいや、神山町の林業を守る「神山しずくプロジェクト」の事務所にも訪問した。3日目は、3つの問い(① 町内で減農薬・有機農業などをどう推進していくか? ② 過疎高齢化が進む中で、里山の暮らしと農業をどう守り維持していくか? ③ 神山町の食材(すだち、梅など)の魅力を、どう全国にアピールするか?)に分かれてグループをつくり、翌日の発表に向けて、グループごとにフィールドワークと発表準備を行った。最終日の4日目は、地域の方々も交えて、成果発表会を行った。


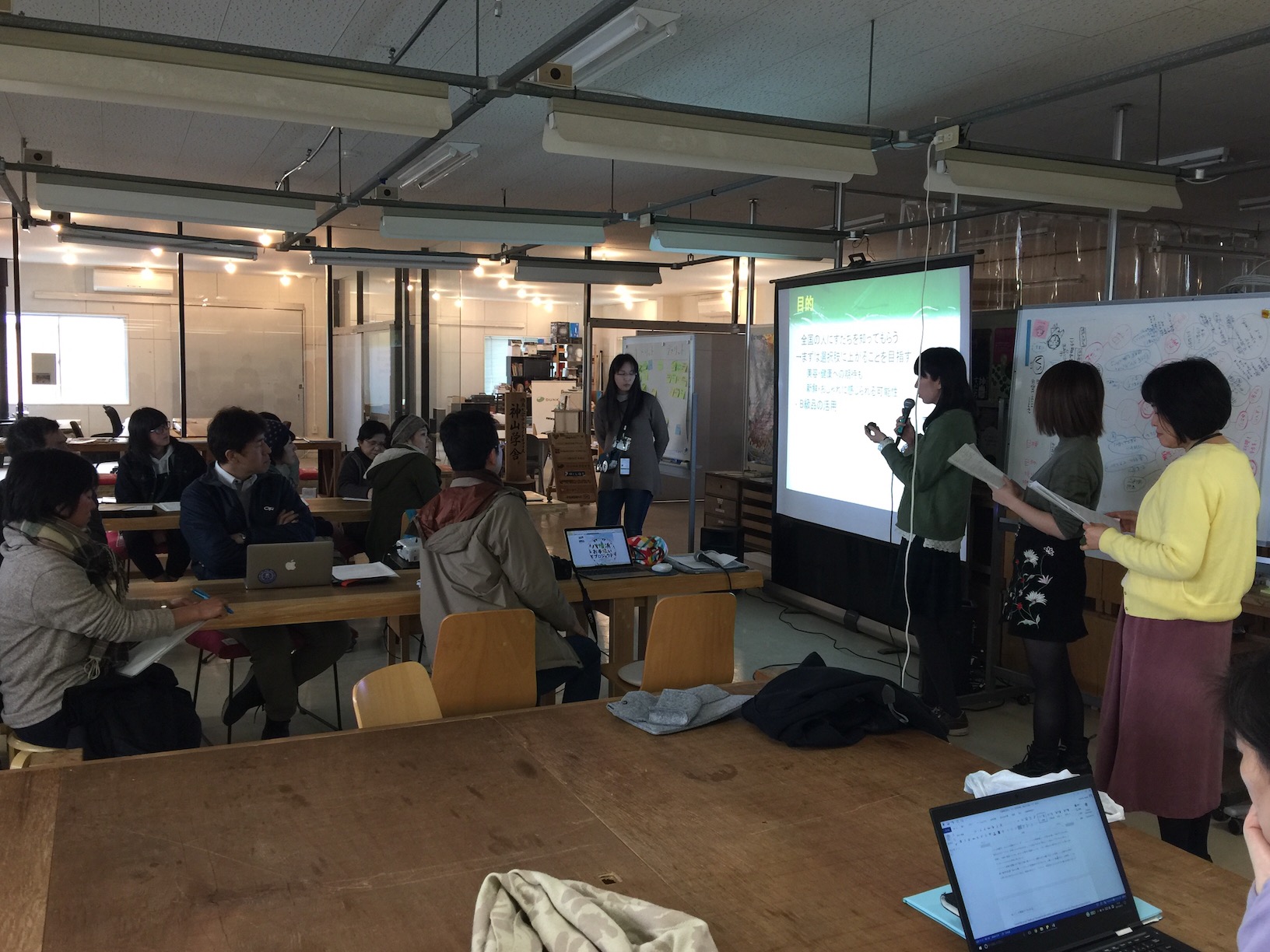
この研修の中で、個人的に関心を持ったのは、地方再生戦略のひとつである「フードハブ・プロジェクト」である。フードハブ(Food Hub)とは、アメリカ合衆国農務省も推奨している考え方で、地域のフードハブという意味では「主に地元の名前が特定できる生産者たちの食品を、集約、保存、流通、そしてマーケティングすることで彼らの能力を強化し、卸売業者や小売、制度的な需要に積極的に応えるビジネス、または組織のこと」(http://foodhub.co.jp/about/project)と定義される。神山町のフードハブ・プロジェクトが掲げる「地産地食(Farm Local, Eat Local)」というモットーは、この考え方を如実に示しているといえよう。通常は「地産地消」という表現を使うが、過疎の進む農村では大きな「消費」は望めないため、生産と消費はアンバランスな関係になってしまう。したがって不特定多数の人々の消費のために生産するのではなく、地域の人々が食べるために生産する、というのが「地産地食」の企図するところである。これにより、生産から消費までを一方通行の営みと捉えるのではなく、「小さいものと小さいもの、少量の生産と少量の消費をつなぐ」流通の仕組みを整え、「『食べる』循環」の一環として生産活動を捉え直すのである。彼らはこの循環を「育てる、つくる、食べる、つなぐ」と名付けていた。


農業再生、または「地産地消(地産地食)」が取り上げられるとき、一般には農業従事者の育成や農業のあり方といった生産部門にスポットが当たることが多い。しかし今回、関係者の方々にお話をうかがって強く感じたのは、この循環を円滑に行うためは流通部門、すなわちマーケティングやマネジメント等のサポートが非常に重要である、ということだった。なぜならこの循環がうまく回るためには、生産量と消費量の適切なマッチングとコントロールが不可欠だからだ。神山町のフードハブ・プロジェクトの場合、共同出資者でもある株式会社モノサスがこの縁の下の役割を担っている。モノサスは、東京に本社を置く会社で、ウェブデザインや、ウェブを使ったビジネスのプランニングやマーケティングを行うエキスパート集団である。神山町にはサテライトオフィスがあり、プロジェクトに関わる社員は、そのオフィスの所属という扱いになっている。説明の中では、例えば食堂ひとつとっても、コンビニエンスストア等で利用されるマーケティングデータからの推計により規模の設計を行ったとのことで、実際日販もほぼシミュレーション通りなのだという。「地域の食材を提供する」というコンセプトだけで、とにかく箱モノを作ればなんとかなるだろう、というやり方とは大違いである。土に根ざした昔ながらの営みを、最先端の技術を駆使した緻密な計画によって支えているという意味でも非常に興味深い。さらにこうした循環を深化させることは、農業に従事しなくてもこの町で生活の糧を得て暮らしていけるという意味で、町の子どもたちの職業選択の幅を広げることにもつながるだろう。選択肢が農業だけしかないならば、それ以外の職業に就きたい若者は町を出るしかない。しかし例えば経営学やITの知識を活かして、町の農業を間接的に支えることで収入を得られることが分かれば、町に残る若者やUターン者も増えるかもしれない。近年では、MOOC(Massive Open Online Course)が発達し、ネット回線さえあれば、いつでもどこでも世界最先端の講義が受けられる環境が整ってきている。高速ブロードバンド網を持つ神山町なら学習の設備環境も申し分ない。そうした点からも、このプロジェクトは農業再生以上のメリットがあるように思われた。
ところで、画期的な町づくりに取り組む神山町をこの時期に覆っていたのは、大量のスギ花粉であった。高度経済成長期、住宅需要を見込んだ国の政策により、神山町にも大量のスギが植えられたが、経済成長の鈍化や海外からの安い木材供給が進んだことでそのスギは切り倒されず、今となってはスギ花粉が大量に飛ぶ始末。山のきれいな空気を吸いに来たはずなのに、花粉症の参加者たちは非常に辛そうだった。さらに間伐されない人工林は、山の保水力に寄与するどころか山の水分を吸ってしまうため、ふもとの田畑に流れる川の水量が減少していること、スギは山の動物たちのエサになりにくいことから、イノシシやシカ、サルが民家にまで降りてきて、収穫間近の作物をすべて食べてしまうという獣害が深刻との話も聞いた。持続可能性を考えない、おおざっぱな将来展望に基づく「国策」によって潤うのは国や大企業だけ、地方は利益を得られないどころか、将来にわたって負債を抱え続けるというのは、私が研究のフィールドとしている沖縄でも見慣れた光景である。地方再生とは、地方を搾取しない都市のあり方を含めて議論すべき課題であるともいえるだろう。
報告日:2017年3月29日


