
“Joint Seminar: The University of Tokyo - Freie Universität Berlin” 報告 高村 夏生
- 日時
- 2017年3月1日(水)〜3月10日(金)
- 場所
- ドイツ・ベルリン
- 主催
- 東京大学大学院博士課程教育リーティングプログラム「多文化共生・統合人間学プログラム(IHS)」教育プロジェクト4「多文化共生社会をプロデュースする」教育プロジェクト5「多文化共生と想像力」
今月上旬、ベルリン自由大学にてIHSとのジョイントセミナーが開催された。しかし、本研修はそのセミナーのみならず前後に行われたベルリンにおける諸施設の訪問も含むものであり、いずれも報告者にとっては印象深い体験だったため、合わせてここに報告したい。
報告者の本研修参加の背景
そもそも報告者がこの研修に参加した契機は、Aタームに受講していたIHS開講科目のAcademic Englishであった。この授業は学科との合併科目として開講され、「日本(文化)」が諸分野においてどのように語られてきたのか、主要な文献を元に先生や受講生(その多くは留学生であった)と意見を交わすというものであった。IHSにおけるAcademic Englishの主要目的は英語の総合的なスキルを伸ばすことにあったため、この授業のスピンオフという形で、かねてより交流のあるベルリン自由大学にて、英語でのプレゼンテーション・スキルに特化したセミナーに参加することが企画された。しかし最終的には、顕著な歴史を有するドイツ、ベルリンの諸施設の訪問も含んだ研修が組まれ、当該科目における「国という枠組みにおいてどのように文化が語られるか」という文脈が活かされることとなった。
ベルリンの諸施設の訪問 ─「虐殺されたヨーロッパのユダヤ人のための記念碑」にて ─
ベルリン自由大学でのセミナーを除いて参加者全員が訪問・参加したのは「虐殺されたヨーロッパのユダヤ人のための記念碑(・記念博物館)」、「恐怖政治の見取図」、ベルリンの壁・ツアー、シリア難民によるベルリン・ツアー、マックス・プランク感染生物学研究所である。



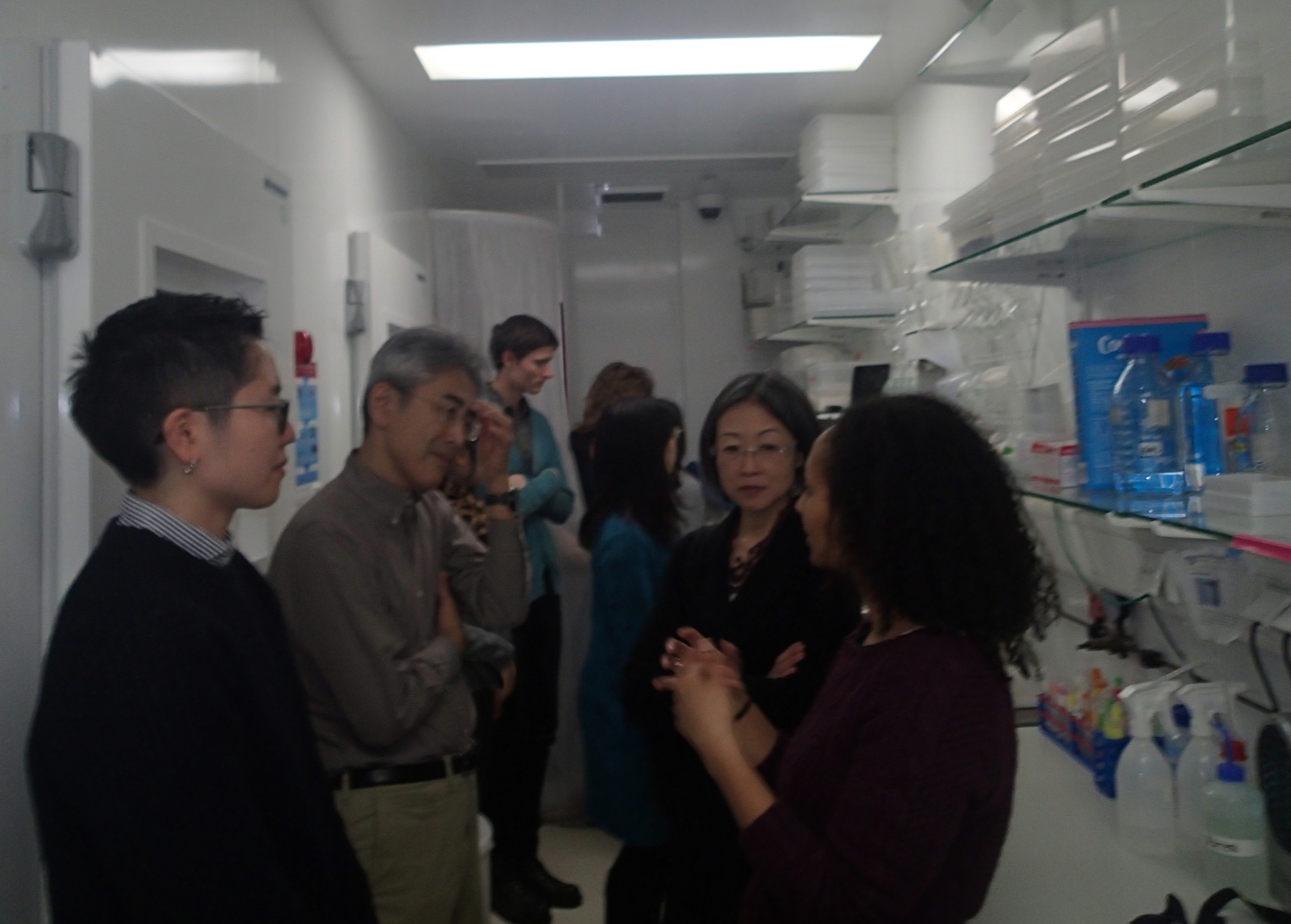
ここではIHSの学生として最も印象的だった、「虐殺されたヨーロッパのユダヤ人のための記念碑」を訪れた感想について述べる。
「虐殺されたヨーロッパのユダヤ人のための記念碑(Memorial to the Murdered Jews of Europe)」では、実はまず、その正式名称にはっとさせられた。私はその施設を「ホロコースト記念碑」という名称で記憶していたのだが、私にとって「ホロコースト」とは、それが第二次世界大戦中に行われた対ユダヤ人虐殺を意味する語彙だと「知って」はいても、遠い異国の史実を指す固有名詞としてどこか自らと隔絶されて感じられる語であった。ところが実際には”murdered “という、自らが生きるのと時を同じくして起きた、種々の残酷な出来事の説明として眼にした(自らにとって)「生きた」語が用いられており、その惨さが肉迫して感じられたのだった。また、記念館ではいかに犠牲者を記憶するかということに焦点が当てられており、彼らの書簡の数々や、ある家族の辿った強制退去・強制収容の道のりが複数のポートレートと共に展示・説明されていたほか、ある部屋では一人一人の名前が短い紹介とその死亡理由と共に延々と読み上げられ続けていた。こうした展示を通じて、記念館の運営のキーワードとして語られた”politics of remembrance”という言葉を重く実感することとなった。
この歴史の記憶の仕方、という点は「恐怖政治の見取図」にも共通して印象的な点だった。先の戦争に関して、日本において広く認知・訪問されている施設の中で、これほど加害(者)、そして被害(者)の様相に正面から取り組んでいる施設はあるだろうか。報告者は広島平和記念資料館、沖縄県平和祈念資料館を訪れたことがあるが、いずれも日本(人)における被害・犠牲が中心である印象を受けた。そしてこの印象は、実は自らが受けた教育について通じるものでもあった。私にとって、戦争についての語りは歴史の授業ではなく、小学校低学年での道徳あるいは特別授業などで触れたのが最初であったと記憶しているが、そこでは数々の凄絶な体験談が語られると共に平和の重要性が強調されていた。各学年における読書感想文の課題図書にもそうした本が並び、そして常に被害者は「無辜の市民」としての日本国民であったような気がする。のちの歴史の授業ではもちろん「歴史」として様々な記述に触れたわけだが、いずれも日本国としての加害という視点やその犠牲となった人々の詳細は、抜け落ちているとは言わずとも「しっかり取り上げられた」という印象はなかった。
これは私にとって、次第に不安に感じられるようになってきたことでもある。「正しい歴史」という言葉ほど、難しく時に恐ろしい言葉も無いかもしれないが、少なくとも多様な視点からの語りは、自分と異なる背景をもつ人と歴史について語る共通の場を確保してくれる。大学に入り、留学生との交流が増えるに従って、私の知っている歴史がどれほど彼らの歴史と同じなのか、とりわけ12月8日が「真珠湾攻撃の日」となりつつあったり、シンガポールの友人から「東大の友達が、日本がシンガポールを侵略したこと知らなかった」と聞いたりする度に、怖さを感じていた。そして、そうした思いを改めて認識したのが「虐殺された…」の訪問後に研修参加者で簡単に感想を共有した時である。参加者の中には中国からの留学生もいたのだが、その学生は、言葉にしづらい(したくない)、できないとしながらも、自らが受けた教育に基づく歴史認識を振り返ったとき、日本人である他の学生と記念碑・記念博物館を見学することに対して何某か思うところがあったようであった。その学生が何を思ったのか、そして何故それをあの場で言葉にしなかったかは、もちろん本人にしかわからないし、推測もすべきでない。しかしこのことをきっかけに、ふと、もし歴史に関わることについて意見を交わそうとする時、その場にいる他者が自分の思うこと・考えることを受け入れる準備がない、同じものを共有していないと感じたら、私は意見を言えるだろうかと思った。特に、自国と相手国が違う場合に。さらには、加害・被害の関係がある場合に。とりわけ先述の自らの歴史認識への不安の裏返しで、私自身がそうした議論に参加する資格があるのか、省みずにはいられなかった。
確かに「虐殺されたヨーロッパのユダヤ人のための記念碑」については批判が存在するのも事実である。しかし「恐怖政治の見取図」も含め、それらが複数の視点からの情報を提供し、かつ無料で広く開かれ、利用されていることはとても重要であると感じた。それらは共通認識、あるいは少なくとも、先の大戦について「何が起きたのか」、議論する場を提供していると思う。歴史は「過去」であるが、それこそが現在を形作るものでもあるため、どのような歴史の語られ方が望むべきものなのか、そして日本における現状とその理想との隔たりはどうであるのか、改めて考える必要があると思った。

ベルリン自由大学におけるプレゼンテーション・セミナー
本研修の主眼であったベルリン自由大学におけるプレゼンテーション・セミナーは、2日間という短い時間ではあったが実線重視の内容でとても良いセミナーであった。特に、これまで参加した類似のセミナーではプレゼンテーションの中身のみに焦点を当てたものが多かったところ、話し「方」(目線や立ち姿、手の動きや声音、ボディ・ランゲージ全体)にも配慮した内容であったのは新鮮だった。私の専攻は生命科学であるが、しばしば「何を言うかが大事であって、どう言うかは二の次である」という姿勢が見受けられることがある。実際、どう言おうが「データが語る」部分もあるため、こと専門家同士であるならその姿勢も間違いでは無いだろうが、その積み重ねが、一部において専門家とそれ以外とのコミュニケーションを難しくしているとも感じるのである。聴衆が専門家でない場合、話者の話し方が話す内容への印象、理解を大きく作用することは経験的も確かであると思うので、今回それらも含めたセミナー内容となっていたのは大変有用であった。とりわけ、セミナーの中では一人ずつ前に出て話し、広くフィードバックをもらう機会が多く設けられていたため、自覚できていない改善点を多く指摘してもらうことができた。目線を逸らしてしまう、手で髪を触ってしまうなどは「人前」というプレッシャー下で出てしまうものであり、特に今回は準備していない内容について話すという、最も自分が緊張するシチュエーションで行われたので、自主練では知り得ない自分の欠点をよく知る機会となった。また、他の人にフィードバックを行うことで、何に気をつけるべきかについてより注意を払う時間が持てたのも良かったと思う。
しかし当然、プレゼンテーションのスキルは「わかっているけどできない」ことの方が多く、経験及び練習、「訓練」しか改善方法が無い場合がほとんどである。もちろん自分での練習も相当の効果があるものの、先述のように人前での経験には代え難いものがある。小・中・高ではプレゼンテーションに関する講義を受けたことは全く無く、大学でも特化した授業は稀にしか受けることができなかったので、IHSに関わらず学内でこうした機会がもっと増えると良いと思った。また、そうしたスキルは個人のキャリア形成に有用(必須)であるだけでなく、最終的には専門分野の社会的プレゼンスを向上させることにも繋がるだろう。


ベルリン自由大学とIHSの学生による合同ワークショップ
研修中には、本セミナーでの学びを実践する場として、プレゼンテーションを行う機会も設けられていた。過去行われた際には参加者が各自の専門分野について紹介したそうだが、今回IHSの学生は”Higher Education”を共通テーマに据え、加えて二人一組みのチームで事前に調査を行い発表するという形式がとられた。
しかしこの準備が難航を極めた。”Higher Education”というのは重要なキーワードであり、昨今の大学改革を受けても、またリーディング大学院という環境で学ぶ身としても、参加者の誰もが考えねばならないテーマである。一方で、本セミナーはあくまで先述のAcademic Englishの延長として企画されたため、準備の過程で高等教育について体系的に学ぶ機会というのは設けられていなかった。そのため、参加者の間に共通の問題意識や関心が形成されることがなく、発表テーマは”Higher Education”から想起される各人の関心に委ねられ、かつチーム発表でもあることから、各々異なる関心を擦り合わせて一つの形にするというプロセスを経て決められた。
私のチームの最初の問題はテーマ設定にあった。”Higher Education”について、私の興味は科学技術政策と高等教育の関係にあり、もう一人は高等教育が産業に与える影響について関心があったが、いずれにせよ話が大きく的を絞れずにいたのである。一方、事前準備の段階でマックス・プランク研究機構と理研の違いについて繰り返し関心が寄せられていたため、高等教育からは離れてしまうものの、最終的に「機関」に焦点をあて、各々の関心につなげる形でマックス・プランク研究機構と理研、フラウンホーファー研究機構と産総研の比較を試みることにした。しかし、この「比較」も難しかったのである。私たちにはこれら諸機関について関心はあったが問題意識が薄かったため、軸をどこに設定し何について比較すれば良いのか途方にくれてしまったのだ。問題意識の無いところにテーマを設定したのが全ての過ちの始まりであったが引き返す時間もなく、当然、プレゼンテーション・セミナー中のプレ発表時には「結論は何?」と言われる始末であった。そこに至って、とにかく「プレゼンテーションを行う」ことを目的に結論を「探す」こととなり、フラウンホーファー研究機構と産総研に関しては、前者が「フラウンホーファーモデル」と呼ばれる特徴的な運営方法により産学連携を促進することで知られていたため、研究成果の社会還元という軸立てを見出すことができたものの、マックス・プランク研究機構と理研に関しては依然難しかった。どちらも基礎研究の主要な研究機関ではあるものの、規模も運営資金も国におけるプレゼンスも異なっており、それらを踏まえて比較できるようなアウトプットの差も、明確な問題も見つけられなかったのである。そこで最終的に、フラウンホーファーと産総研で違いの見えた技術移転にテーマを設定し直し、マックス・プランク研究所と理研においてはどちらも問題は無いながらも類似の取り組みで一定の成功を収めていることを紹介するに留めることにした。
しかし突貫工事のような形で決めた内容である。最後まで中身の資料準備にかかりきることとなり、練習の時間を持つことができなかった。当然、発表時にセミナーで受けたアドバイスに配慮する余裕は一切なく、内容の説明で手一杯となってしまい、さらにチームの英語力も影響して辛うじて決めた結論さえ満足に説明できないことになってしまった。
加えて、事前に正しく認識できていなかったのだが、発表におけるIHS以外の参加者はいずれも社会科学を専攻している学生及び先生のようであった。一般に向けて話すという想定のもと、技術移転というテーマに関心を持ってもらうためのイントロダクションとして用いた「科学技術が人々の生活を便利にして『より良い生活に資する』」という表現自体が問題視され、加えて公的資金を投入した研究と産業が連携するという前提自体に質問が来ることになってしまった。「自分の分野での『当然』が他分野では異端」ということはよくある話であり、そこまで抽象化すればとても教育的な経験ができたと言えるものの、一方で参加者の側に「社会科学の前提に則って説明すること」が期待されていた印象もあり、このプレゼンテーションの場自体がどういう目的で設定されていたのか、些か混乱したのも事実である。最後に先生が仰ったように、プレゼンテーションは聴衆の「時間をとって」行われるものだからこそ、可能な限りプレゼンターと聴衆が、その場の性質について共通認識を持つことは重要だろう。今回の失敗は間違いなく「準備不足」ではあるものの、それで片付けるには惜しいほどの時間と労力を割いて臨んだため、改めてそれ以外の点を省みると、聴衆にエンゲージするのはプレゼンターの役割であるからこそ、事前に「どのような」人が聞いてくれるのか確認をしなかったのは大きな反省点だと思う。さらに今回に限って言えば、確認できていたとして、それに対応したプレゼンテーションが組めていたかという問題がある。と言うのも、私にとってより身近である科学コミュニケーションにおいては、聴衆の「前提」として彼らが「知らない」ことを意味する場合が少なからずあるが、今回多くの想定外の質問を受けたのは、知っている/知らないによる齟齬というより、異なる「規律」で考えていることに由来するように思われたからだ。この、他の専門の「規律」に関して、IHSでは「基礎科学」「人文学」「社会科学」の大きく3分野について入門講義を開講しており(リテラシー科目)、実際私は社会科学を受講していたものの、それらを実感するのは講義内容および時間の制約を考えても難しかった。IHSに所属した当初から、「多文化共生と言っても、参加者自体が共生できていない」という見解は広く共有されており、読書会等を通じて専門に基づいた交流の機会を設けていたが、今回のプレゼンテーションの反省を通じて、そうした取組みが不十分であったと認識するに至った。


研修全体を通じて
今回のベルリン研修では、それぞれの場所における参加・訪問目的は異なっていたものの、全体を通してこれまで自分が学んできたことを省みる機会となった。当初主眼にあった英語のスキルについては、セミナーで指摘された点だけでなく、カウンターパートであったベルリン自由大学の学生とのレベル差に「標準」を知る思いであったし、かねてから漠然と不安を抱えていた自身の歴史認識やそれが形成されるに至った経緯については、ベルリンでの諸施設の訪問を通じてより具体的な問い立てをする契機を得たように思う。加えて合同ワークショップでは、テーマ設定のプロセスのみならず、他分野との共同という点でも自分の未熟さを痛感することとなった。とりわけ、IHSで2年を終えようとしている今になって、先述の通り”Higher Education”という重要なテーマにリサーチクエスチョンが出せなかったこと、社会科学における考え方を全く考慮できていなかったことは、この期間の自分の学習姿勢を問うのに十分な事実だったように思う。しかし省みるだけでは何も変わらない。まだ模索している部分も多いものの、3年目に向け徐々に実践として行動に移していきたいと思う。
報告日:2017年3月24日


