
2015年度学生自主企画「沖縄企画」報告会 報告 宮田 晃碩
- 日時
- 2016年5月20日(金)5限(16:50 - 18:35)
- 場所
- 駒場キャンパス8号館205教室
- 報告者
- 2015年度学生自主企画「沖縄企画」参加学生:崎濱紗奈、山田理絵、菊池魁人、半田ゆり、吉田直子、李依真
- 主催
- 東京大学大学院博士課程教育リーディングプログラム「多文化共生・統合人間学プログラム(IHS)」教育プロジェクト2「共生のプラクシス──市民社会と地域という思想」
「沖縄企画」の報告会はそれ自体興味深いものであった。現地へ赴き「沖縄問題」に多角的に取り組み、それをより普遍的な関心へ敷衍していくというのが当企画の主旨であったが、そうするとこの報告会は、まさにその「普遍化」の可能性を示す場でもあったわけである。直接参加していない私自身は、この報告会から何を受け取ることができたか。それは私自身の問題でもあるけれども、私がそこで得たもの、考えたことを記すことは、当企画が本来志向した可能性を示すことにもなると思う。
私が何を関心としてこの報告会に臨んだかといえば、それは「現場に行くということは知的営為にとってどのような意義を持ちうるだろうか」ということである。例えば私がもし沖縄の研究を専門としていたならば、そこに行くことでしか得られないような資料や情報があるかもしれない。しかし例えば日本の政治状況における沖縄の問題、というような観点から取り組むとすれば、敢えて現場に行かなければ分からないこととは、一体何なのだろうか。「現場の声」といったものは、一体いかなる意味で尊重されるべきなのだろうか。「沖縄問題を普遍的な問題へと敷衍する」というとき重要なのは、私が思うに、個別的な場所からより一般的な問題を「見えるようにする」ということなのだ。単に問題を抽象化して他に当て嵌まるようにするというのであれば、その場所の個別性、敢えてその場所を訪れることの固有の意義は薄れてしまう。そうではなく寧ろ、具体的な視点を獲得するということが肝心なのだ。我々は必ず何らかのパースペクティヴにおいて物事を見ているはずなのだが、このことはとりわけ価値中立的な学問に取り組む中で忘れられ、あるいは極力捨象される。だからこそ具体的なパースペクティヴを選び取り、反省的な態度を保ちつつそこに自ら身を置いてみることは、重大な意義を持つ。沖縄を見るというだけでなく、沖縄から見るということ、沖縄から語るということ、このことが当企画では目指されていたように思う。そうだとすれば、もう一つの課題は「沖縄から語られたことはどのように聞かれるか」ということであろう。私は一体何を聞き取っただろうか。報告会で語られたことの中でも私自身の印象に残ったことを三つほど取り上げてみたい。
例えば第一に、戦没者の遺骨を収集されている国吉さんの私設の「戦争資料館」は興味深いものだった。それはモノを年代によって分類したりせず、無造作に並べたところである。手榴弾や薬瓶、飯盒などの遺物が並べられているが、そのスペースは殆ど事務所と一体化している。無造作な展示と国吉さんの淡々とした語りは、博物館のように分節化した見せ方とは全く違うリアリティを感じさせたということであった。こうした、モノの(文字通り)有無を言わさぬ存在というのは、情報に還元されるものではない。それはただ客体として把捉されるものではなく、それどころか私の「知る」という働きの奥底に呼びかけ、「何をどのように知るべきか」導くようなものだろうと思われる。
第二の例は、モノの端的な存在感という点で、第一の例と通ずる。それは米軍基地のフェンスに結びつけられる赤いテープである。反基地運動の一環としてテープは結び付けられ、ときに文字を形成してメッセージを書くこともある。しかし明確なメッセージを書かずとも、それは謂わば嫌がらせのようなもので、ひたすら続けることが示威行為になる。私はどちらの立場を支持するというのでもないが、この行為は興味深く思われた。フェンスに結びつけられるテープをめぐって、人々が“交流”する。「反・反基地」の人々(あるいはただ景観を損なうことを厭う人々も含まれるかもしれない)はテープを剥がす。もちろん米軍の兵士もテープを剥がす。このテープは意味を持たない、象形文字以前の「結び目」に似ている。意味というものは予め取り決めがあって成り立つものだが、このテープはそうした「意味」なしにただ自らの存在を主張するのである。
第三に、当企画の一環として開かれたワークショップについて、これが沖縄大学の、普段は学生の談話室として使われるスペースで開かれたことは、些細なようで意義深く思われる。普段使われている場所に身を置き議論するというのは、少なからず「そこからの眺め」を共有することに資するだろう。同じ問題が場所を変えると違った相で見えてくるということは、しばしばある。当企画に参加された吉田さんは「沖縄問題」に新しい風を呼び入れるということを、このワークショップの意図の一つとして指摘されていた。そのようにして、ある場所に様々な分野の専門家が集まるということは、「そこからの眺め」を豊かにすることに繋がるだろう。意義深いワークショップを開催された方々に、敬意を表したい。これはもちろんワークショップに限ったことではない。例えば「語り部」として過去を伝える人から話を聞くということは、単に一連の経験を知るというだけのことではなくて、まさにその場で経験するということなのだ。実際の経験とそれを伝え聞くこととの間には、当然懸隔がある。しかしそうした懸隔も含めて、その場でモノに触れ語りを聞くということは、自分自身の経験に他ならない。
こうして私は報告会で、「沖縄での経験」を聞いたのだった。加えて、当企画が継続して既に二度目の訪問を果たしたということは重要だと感じた。企画の参加者である半田さんが「現場に立ち続けること」「黙って隣に立つという形での共生」と表現されていたことが印象に残っている。それは沖縄という現実を自分の中に息づかせることだろう。「現場に行く」ということ、あるいは「現場に佇む」ということは、そこで思考し、そこから思考するという固有の意義を持ちうる。
私はこの企画に参加していない。現場に行っていない。一体私は何を語っているのだろう。理念的なことを理念的に語っているに過ぎないとも思われる。しかし確かに、私には、「沖縄から語っている」ということが現実に感じられた。それはおそらく、当企画に参加された方たちが既に「沖縄に立つ」人たちであったからだろう。してみると現場を訪れることは確かに、自らの経験を豊かにするばかりでなく、未だそこを訪れていない人たちへとその現場を現実のものとして語り示すという可能性を持っているのである。

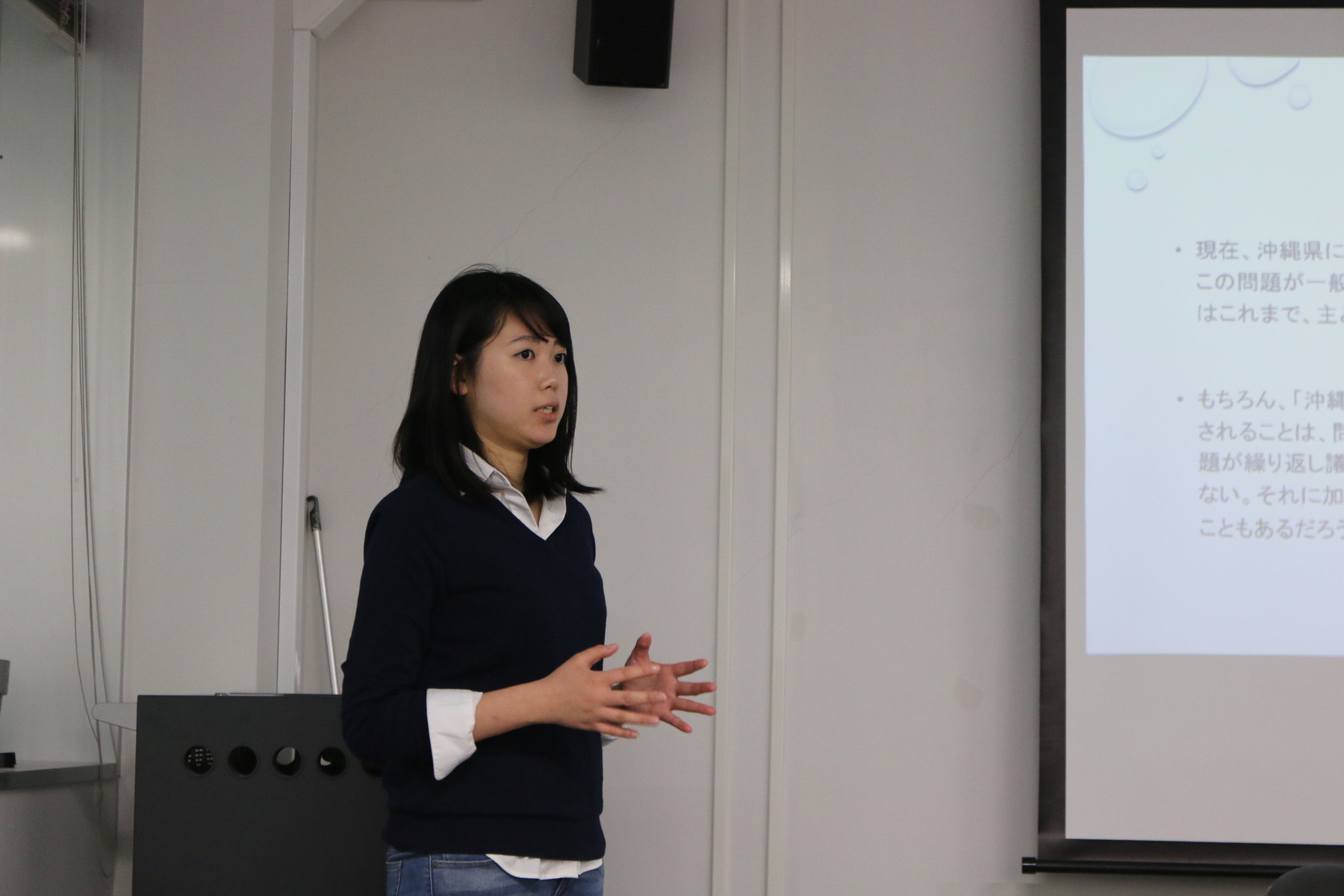



報告日:2016年6月4日


