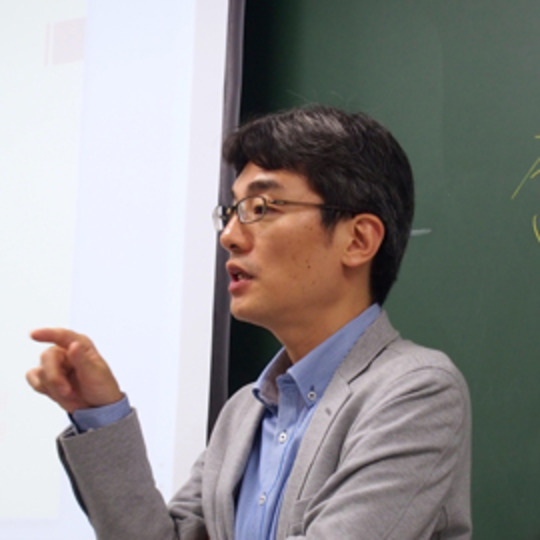
多文化共生・統合人間学演習IX(第1回報告) 髙邉 賢史
- 日時
- 2014年10月24日(金)16:30−18:00
- 場所
- 東京大学駒場キャンパス8号館205教室
- 講演者
- 石井剛(総合文化研究科地域文化研究専攻)
- 主催
- 東京大学大学院博士課程教育リーディングプログラム「多文化共生・統合人間学プログラム(IHS)」教育プロジェクト2「共生のプラクシス──市民社会と地域という思想」
多文化共生・統合人間学演習IXの第1回として,中国近代思想史・哲学をご専門とされている石井剛准教授に「中国の地震災害と市民社会」というタイトルでご講演頂いた。本講演は11月に実施される「四川-福島ワークショップ」のガイダンスを兼ねたものである。
中国は日本と並ぶ地震国の1つである。近年では死者7万人を出した2008年の四川「5.12」大地震(汶川地震)を初めとして、2010年の玉樹地震、2012年の彝良地震等、四川省を中心とした中国西南部でマグニチュード7前後の地震が頻発している。中国西南部はその地理的要因、経済的要因、そして多民族性から地震被害の低減と発災後の救助活動が課題となっている。
汶川地震では政府による初のマス・メディアの報道自由化とボランティアによるソーシャル・ネットワーク・サービスを介した情報発信による「全民参加、全民発信」型報道が行われた。これは24万人を超える死者を出した唐山地震(1976年)に関する報道が規制されたことに鑑みれば特筆すべき事項である。メディアが連日政府指導者の陣頭指揮や人民解放軍による救助活動の様子を報じた結果、人々は楊早の指摘する「大きな憐れみと無力感」、「被災地と被災者への関心」からなる「ある種の熱狂」に包まれた。
汶川地震に対する国民の多大な関心は募金活動やボランティア活動として発露したが、以下に挙げるような社会的課題を残した。許紀霖によれば、(1)ボランティアの組織化が未整備であり、(2)多大な関心は動員型募金といった「愛心(思いやり)」の強制を生み、(3)教師が生徒をかばうべきかといった倫理的問題が提起された。また、報道に関しては(4)自由化が被災者への負荷を増大させた一方、批判機能は不全であったと評された。
以上で示した政府の試みと国民の反応は様々な課題を露呈させたとはいえ、汶川地震が従来の局所的、閉鎖的対応や反応からの転換点となったことは間違いない。実際に後発の地震では組織化されたNGOが復興支援に貢献する等、中国の地震災害と市民社会の関係は変化しつつある。最後に、中国における「人民」は階級的要素を潜在的に含意する一方で、中国の伝統社会が血縁の親疎に則った「同心円型」社会関係を基盤とするため、中国では個人の基本的権利を有する「公民」(市民)は存在しないという賈西津の論文を引用する形で、中国における「市民社会」の可能性が検討された。
石井准教授による講義から、我々は現代中国社会の多種多様な課題が地震災害を通じて発現していることに気づく。質疑応答において論点の1つとなったのは、マス・メディアの報道のあり方である。我々から見れば――そして中国人研究者が指摘するように――一連の報道は一種のプロパガンダとも感じ取れる一方で、地震によりコミュニティが破壊された被災者には大きな励ましとなったことは想像に難くない。ここに、災害におけるメディアの役割を論じる上での困難が存在すると思われる。また、救助活動における日本人と中国人の「犠牲」観の差異に関して、人民解放軍と日本の旧帝国陸軍の「英雄」の類似性や、美談の渇望による犠牲の再生産プロセス等の鋭い指摘がなされた。
東日本大震災においてそうであったように、人文学や哲学は災害を通じてその意義を問われる。それに対して機能主義的立場に陥らず逆説的に「何ができないか」という観点から考えるべきである、そして、この問題は答えが容易に出せないからこそ取り組むべきである、という石井准教授の言葉をもって講義は終了した。個人的には日中の災害救助を巡る社会性の差異の大きさを認識し、救助システムの単なる置換では中国における諸問題の解決が困難であると改めて感じた。その克服には現場に共感したシステム構築が重要であろう。また、人文学や哲学の意義や市民社会を巡る問題も、被災者や救助関係者の視点から問い直すことで新たな展開が期待される。私はこれらの点から「四川-福島ワークショップ」は重要な場であると考えている。ワークショップが以上のような課題への突破口となることを願っている。



